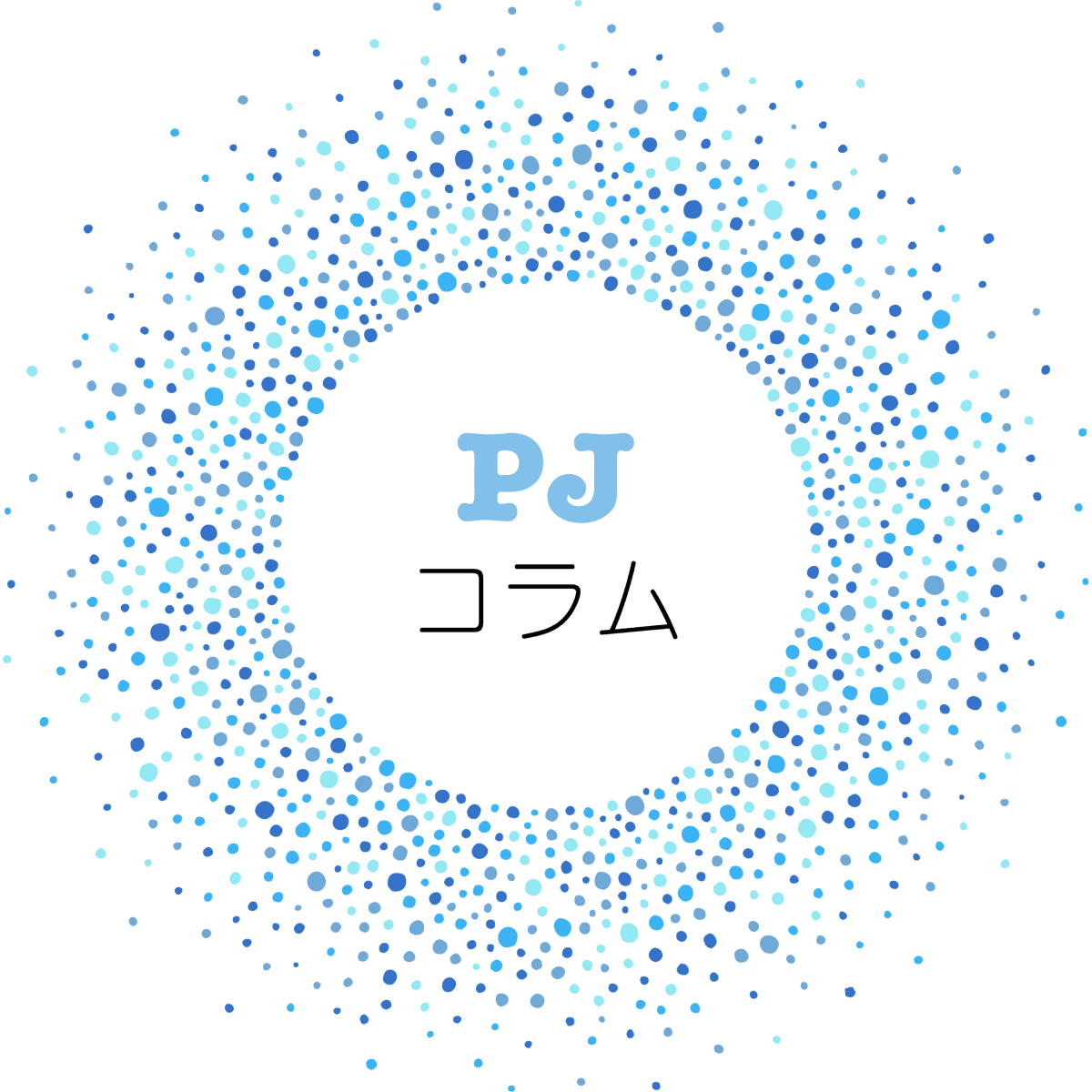
まったく同じ内容であっても、読み書き言葉ではなく、話し言葉で説明して欲しいという一定数のニーズが存在する。活字離れが進み、Youtubeのような動画コンテンツが爆発的に普及した所以だろう。記憶への定着度合いはともかく、未知のことは誰かに説明してもらうほうが理解が進みやすい。今年4月から白井グループ・滝口氏が司会を務めるオンライン勉強会に、プラジャーナルとしても企画・運営に携わっている。つい先日は、「再資源化事業等高度化法」を環境省廃棄物規制課の松田課長から直接解説いただく機会を設けた。
▼この新法は、検討開始からわずか1年で国会で成立、公布された。既存の廃掃法やリサイクル法を改正するのは大工事になるため、非効率だった部分などを特例的に国が認定していくなどし、従来の枠組みを超えようとしたところに大きな特徴がある。施行から3年で、100件以上の認定件数を目標に掲げている。大前提である廃棄物の適正処理を守りながら、資源循環ビジネスに取り組む事業者を法的・財政的に支援していくとのことだ。
▼気になるのが、既存の廃棄物業者への影響だ。年間処理量が概ね1万トンを超える処理業者(「特定産廃処分業者」と呼ぶ)に課される報告制度。産廃の種類や処分方法ごとに処分数量と再資源化を実施した量を、毎年度、環境大臣に報告する義務がある。目的の一つは「さんぱいくん」などの情報基盤と連携し、製造業者とのマッチング機会を創出する。もう一つは、基準に照らして不足している場合には必要な措置を取るよう勧告ができる。何をもって不足、問題とするのかは、「基本方針」や「判断の基準」について政省令で決める。それも公開の場で検討を進めていくそうだ。
2026年01月26日【環境省】自動車リサイクル制度の課題や今後の方向性を議論ASR再資源化や資源回収インセンティブ制度の状況共有
2026年01月26日【出光興産/CRJ】年間処理能力2万tの油化ケミカルリサイクルプラント竣工廃プラの前処理設備併設、回収インフラ企業と連携拡大も
2026年01月26日【協和産業】洗浄粉砕装置のパイオニアが描くプラスチックリサイクルメーカー視点を強みに、製品開発や成形加工にも参画
2026年01月27日【経済産業省】化審法の規定変更、BAT報告でリサイクル材は一部緩和も
2026年01月26日【2026年1月のPETボトル市況】事業系は横ばいも、供給過多の関東でじり安家庭系の容リ入札では、R2規制緩和が焦点に
2026年01月26日 コラム
欧州で、ELV規則が暫定合意に至った。これまでも、世界の環境規制に大きな影響を与えてきたEUの決断とあっては、[...]
2026年01月14日 コラム
新年の風物詩となったマグロの初競りで、寿司チェーン・すしざんまいを運営する㈱喜代村が青森・大間産のクロマグロを[...]
2025年12月22日 コラム
12月10~12日に、東京ビッグサイト・東ホールで実施された「エコプロ2025」。SDGsWeek EXPO2[...]
2025年12月15日 コラム
環境省は、循環経済への本格的な移行に向け、「再生プラスチック集約拠点構想」を描いているという。これは、既存の再[...]
