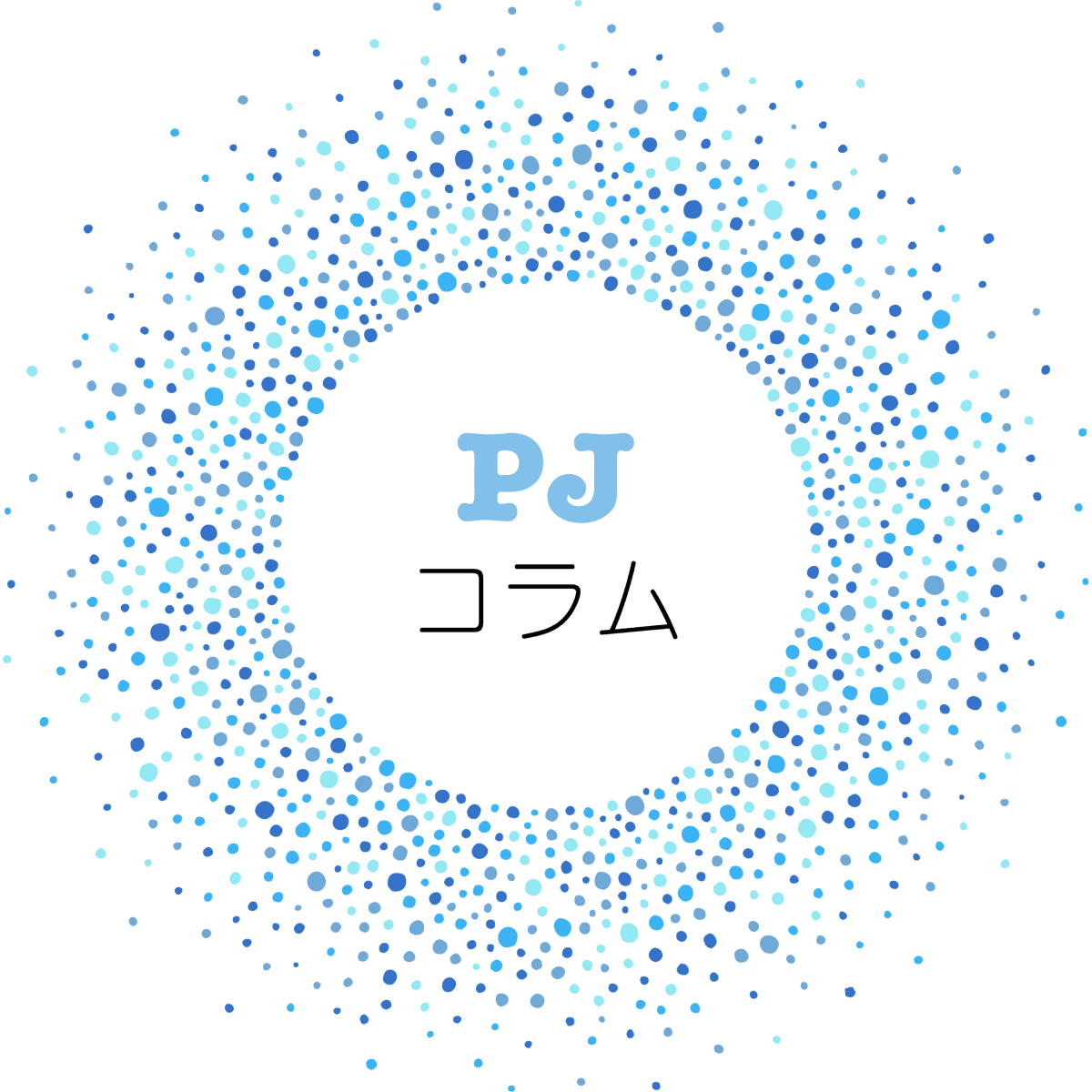
プラスチックのリサイクル実証実験が花ざかりである。
消費財メーカーが中心的な役割を担って、消費者に渡ったプラ包装を専用の回収ボックスを商業施設などに置いて回収。集まったものを選別・破砕・洗浄・ペレット化し、再びプラ包装の原料として使おうというものだ。
PETボトルではボトルtoボトルのリサイクルが実現し、再生ボトルをコンビニで目にするようになった。マテリアルからマテリアルの水平リサイクルは消費者にとって分かりやすく、環境に良いことしていると印象づけるPR効果は大きい。
しかし、実際にはプラ包装全般での水平リサイクルは課題も多い。課題だらけといっても過言ではない。各企業は社会実装していこうというより、広告宣伝としてのリサイクルの域を超えないのではないか。
1つはコストが膨らみ過ぎることだ。一カ所の回収拠点から数十キロのものを集めようというのは物流効率が悪い。せめて1度の回収あたり200キロ、300キロは欲しいところだが店舗のバックヤードにそこまでスペースがないことも多い。高コストなサプライチェーンが持続可能ではないのは明らかで、誰がそのコスト負担するのかという問題にも直面する。
2つ目は、なぜ水平リサイクルでなければならないのか?その方向性は必ずしも絶対ではないはずだ。プラ特有の物性劣化を考慮すると、原料に多用出来るわけではなく、消費者に一度渡ったものは異物混入のリスクも高く、安定性に欠ける。そもそもニーズのない原料を作り出そうとしているのだ。マテリアルリサイクルに囚われ過ぎず、手法は柔軟に選択すべきである。
3つ目は、既にプラ容器包装は容リ法にもとづき、20年超にわたり、自治体が効率的に収集し、処理される仕組みが築かれてきた。プラ包装を使用する企業は年間約2500億円もの委託費を負担し、容リ協会がリサイクルを代行してきたのである。この容リ法は5年に一度見直しをかける制度でもある。特定事業者が集め方や用途を拡充したいのであらば、このプロセスを活用した見直し議論も期待したい。
再生原料のリサイクルの原動力となるのは、コストと代替性にある。バージン原料に比べ、安いコストで調達でき、代替えしても同じ性能を保てるか、あるいは近づけられるかがリサイクル継続のカギである。その結果、環境負荷も減らせるのである。各企業が独自にプラ回収の取り組みを始めることは無駄ではないが、ESGブームの中での一時的な株主対策やプラ包装商品を購入する消費者の罪悪感払拭のためであっては続かない。リサイクルの仕組みとして定着させることを目論むべきなのである。
2026年01月26日【環境省】自動車リサイクル制度の課題や今後の方向性を議論ASR再資源化や資源回収インセンティブ制度の状況共有
2026年01月26日【出光興産/CRJ】年間処理能力2万tの油化ケミカルリサイクルプラント竣工廃プラの前処理設備併設、回収インフラ企業と連携拡大も
2026年01月26日【協和産業】洗浄粉砕装置のパイオニアが描くプラスチックリサイクルメーカー視点を強みに、製品開発や成形加工にも参画
2026年01月27日【経済産業省】化審法の規定変更、BAT報告でリサイクル材は一部緩和も
2024年01月26日【シタラ興産】埼玉で一廃・産廃焼却施設に122億円投資2027年に稼働予定、年間1万5000MWの発電も
2026年01月26日 コラム
欧州で、ELV規則が暫定合意に至った。これまでも、世界の環境規制に大きな影響を与えてきたEUの決断とあっては、[...]
2026年01月14日 コラム
新年の風物詩となったマグロの初競りで、寿司チェーン・すしざんまいを運営する㈱喜代村が青森・大間産のクロマグロを[...]
2025年12月22日 コラム
12月10~12日に、東京ビッグサイト・東ホールで実施された「エコプロ2025」。SDGsWeek EXPO2[...]
2025年12月15日 コラム
環境省は、循環経済への本格的な移行に向け、「再生プラスチック集約拠点構想」を描いているという。これは、既存の再[...]
